
風邪の日

1795年1月9日、第四代横綱で63連勝の記録を持つ2代目谷風梶之助が風邪で亡くなったことに由来するします。
朝礼ネタ:1月9日 風邪の日-風邪を引きにくい部屋とは-
(例文)風邪の日-風邪を引きにくい部屋とは-
本日1月9日は「風邪の日」とされています。
1795年に、第四代横綱で63連勝の記録を持つ2代目谷風梶之助が風邪で亡くなったことに由来するようです。
体力のある力士であっても風邪で亡くなってしまうことがあるのですね。
現代では風邪やインフルエンザではそう簡単には亡くなることはありませんが風邪を引くと仕事にも迷惑をかけてしまうし、何より身体のだるい状態が続くのは辛いですよね。
そうならないためにも風邪を引きにくい部屋の特徴について調べてきました。
ポイントは3つです。
1:部屋の気温・湿度は「適度」に設定
この時期は身体を冷やさないようにしようと暖房を強にしてしまいがちですが
暖房し過ぎると、外気との気温差が大きくなりすぎてしまいます
また暖房したことにより、空気が乾燥し、のどを痛める原因にもなります。
温度と同時に湿度をチェックすることが大切です。
目安としてエアコンなど暖房器具の設定温度は、18~20度。
湿度は50~60%を大きく変動しないよう調節しましょう。
この目安を超えた、過剰な暖房や加湿を行うと、かえって身体に負担がかかってしまったり、
カビやダニの繁殖を促してしまったりなどのデメリットが懸念されます。
2:部屋のホコリに注意
ホコリが呼吸器を痛めることがわかっています。
部屋のホコリは、床に直接積もり、その上十数センチの空気中にも滞留します。
冬場の掃除の際には可能な限りホコリを立てないよう、吸わないよう意識を向けることも大事です。
3:換気をマメに行うこと
晴れの日はもちろん、天候の悪い雨の日にも換気を行うことが必要です。
日光の紫外線で晒された空気はインフルエンザウイルスなどまで殺菌してくれます。
また雨の日は天然の加湿器となって部屋を潤してくれます。
以上のことを踏まえることが予防になります。
風邪を引いて仕事に穴を空けない為にも、日々の生活にも気を遣っていきましょう!
カレンダーでみる1月の朝礼ネタ・スピーチ
1月の朝礼ネタ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
日付をクリックで朝礼ネタにとびます
2024年1月 最新のニュース・時事ネタの朝礼・スピーチ
行事や生活でみる1月の朝礼ネタ・スピーチ

仕事始めとは、年始となる1月の上旬の、最初の仕事のことです。

年が明けて初めて書や絵をかく行事です。一般的には1月2日に行われます。

寒中見舞いはがきは、一年の中で最も寒い季節に相手を気遣ってお互いの近況を報告しあう季節の挨拶状として使われたものです。最近では喪中で年賀欠礼したことや訃報が行き届かなかったことへのお詫びを示したり、喪中の相手を気遣うお見舞いなどに使われています。

鏡餅は、新年の神様である「年神様」の依り代(神霊が依り憑く対象物)といわれています。そもそも一連のお正月行事というのは、新年の神様である「年神様」を家に迎えて・もてなし・見送るための行事で、そのお迎えした年神様の居場所が鏡餅といわれています。

「おせち」とは季節の節目に当たる「節(せち)」の日を指す言葉です。かつて平安時代の朝廷は、正月を含む5つの節に「五節会(ごせちえ)」の儀式を行い、特別な料理である「御節供(おせちく)」を神に供えていたことが始まりといわれています。

「しょうかん」と読みます。小寒とは、寒さが徐々に厳しくなる時期であり、農作業の準備や冬の祝祭のための時期です。

「だいかん」と読みます。大寒は、通常、1月20日頃から2月3日頃までの期間を指し、立春の前の節気です。この期間は、寒さが最も厳しくなり、雪や氷が多く見られる時期でもあります。しかし、大寒が終わると、次は立春を迎え、少しずつ春の兆しが現れ始めることになります。

年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、昭和46年から始まりました。

毎年1月と2月は寒さで献血者が減ることから、成人の日に合わせて献血への理解を深めることを目的にキャンペーンを行っています。

毎年1月17日の「防災とボランティアの日」の前後一週間を防災とボランティア週間と定めています。

2005年に環境省が提唱して始まりました。暖房に必要なエネルギー使用量を削減することにより、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。










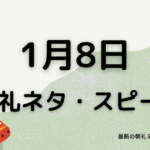
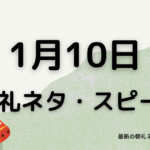
コメント