
血液銀行開業記念日

1951年2月26日は日本で初めて血液銀行が設立された日で『血液銀行開業記念日』と言われています。
朝礼ネタ:2月26日 血液銀行開業記念日-少子高齢化で足りなくなる輸血-
(例文)2月26日 血液銀行開業記念日-少子高齢化で足りなくなる輸血-
2月26日は、1951(昭和26)年に日本で初めて血液銀行が設立された日で『血液銀行開業記念日』と言われています。
血液銀行とは、献血などによって提供者から採取した血液の保存や管理、必要時における輸血の供給を行う機関です。
血液は栄養や酸素の運搬、免疫など人間の生命を維持するのにとても大切です。
現在、血液の機能を完全に代替できる手段はないので、輸血は欠かすことができない治療法となっています。なので、献血によって輸血医療は支えられているのです。
献血で採取された血液は、献血会場から各地のブロック血液センターに運搬され、精密検査や血液成分ごとに分離が行われて血液製剤となり、適切な温度下で保管さます。
医療機関からの要請に24時間365日対応できる体制が整えられており、患者さんが必要とする時に血液が届けられるようになっています。
輸血用血液の多くは、不慮の事故等に伴うものではなく、がん(悪性新生物)の患者さんの治療に使用されており、使用する方の約85%は50歳以上なのです。
しかし現在は少子高齢化などが影響しており、献血をする若年層の減少に歯止めが利かず、高齢化がどんどん進み2015年以降の手術や治療で必要な血液げ不足する恐れがあると言われています。
血液の必要量がピークを迎える27年には、献血者が85万人ほど不足する見通しがされています。
注射が苦手で献血をした事がない方も多いと思いますが、実際献血にかかる時間は受付から採血後の休憩まで、400ml献血で約40分。
針をさしている時間では10分から15分(採取する量によって変わります)で済むようです。
よく、献血に行くとお菓子などが無料で食べられると言いますが、献血のメリットはそれだけではないのです。
通常病院で行う血液検査は1万円前後の費用がかかりますが、献血をすることで健康診断で行う血液検査と同じ項目の数値を無料で知ることができます。
また献血により血を抜かれることで体が血を作ろうと働き、体がぽかぽかしてきます。
そして定期的に血液を出すことで老廃物やドロドロ血液を捨てるデトックス効果にもなります。
『時間が無いから』『針を刺すのが怖いから』と、なかなか行けない献血ですが、輸血を必要としている人のため…プラス、自分の健康を知るチャンスにもなりますので、私も積極的に献血をしていきたいと思います。
風呂の日(毎月26日)

毎月26日はその語呂から風呂の日と制定されています。
朝礼ネタ:毎月26日 風呂の日-絶対にやってはいけない入浴方法-
(例文)毎月26日 風呂の日-絶対にやってはいけない入浴方法-
毎月26日はその語呂から風呂の日と制定されています。
お風呂に入ることでリラックス効果やデトックス効果が得られることがわかっていますが
その効果を無くしてしまう絶対にやってはいけない入浴方法がテレビで特集されていたのでご紹介します。
①硬めのタオルでごしごし身体を洗ってはいけない
身体の皮膚には善玉菌が沢山あり、これが良い香りになる脂肪酸を作り出しています。また、皮膚には水分の蒸発を防ぐ皮脂もあります。
身体を洗いすぎると善玉菌や皮脂が失われてしまい、体臭がきつくなったり乾燥肌になってしまったりすることがわかっています。
②湯船に長く浸かりすぎる
長く湯船に浸かると血圧も下がってリラックスできますが、長湯はお肌によくありません。
お湯に浸かっている状態が続くと皮脂が失われ、乾燥肌になりやすくなるのです。
③入浴中にスマートフォンを見る
スマートフォンを見ると交感神経が活発に働きます。
リラックス効果ぎ出ている副交感神経が優位な時にスマートフォンを見ると交感神経が活発になり、自律神経の乱れを招くのです。
自律神経の乱れは肌荒れやくすみの原因にもなるといわれています。
私もよくやってしまうことばかりですが、せっかくのリラックス時間を無意味な時間にしないように気をつけたいと思います。
カレンダーでみる2月の朝礼ネタ・スピーチ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
日付をクリックで朝礼ネタにとびます
2024年2月 最新のニュース・時事ネタの朝礼・スピーチ
行事や生活でみる2月の朝礼ネタ・スピーチ

節分とは「季節を分ける」という意味で、季節が変わる日のことをいいます。2024年の節分の日は2月3日です。

立春は二十四節気において春の始まりとされます。節分の翌日が立春となります。

毎年1月と2月は寒さで献血者が減ることから、成人の日に合わせて献血への理解を深めることを目的にキャンペーンを行っています。

「資源のエネルギーを大切にする運動本部」が1977年に制定しました。

冬の時期で、特に脳卒中が多発する時期であることから予防週間として制定されています。

2月20日の「アレルギーの日」の前後一週間をアレルギー週間としています、

2005年に環境省が提唱して始まりました。暖房に必要なエネルギー使用量を削減することにより、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。

春節は中国旧暦に基づいているため、毎年日にちが異なります。2024年は2月10日からとされています。











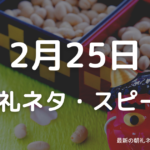
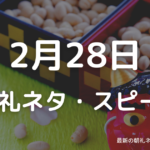
コメント