
涙の日

7月3日は【な(7)み(3)だ】の語呂合わせにちなんで、涙の日と制定されています。スマホやパソコンの普及により、液晶画面を注視する使用時間が年々長くなっていることから、ドライアイケアの必要性
が呼びかけられます。
朝礼ネタ:7月3日 涙の日-疲れ目対策とは?-
(例文)7月3日 涙の日-疲れ目対策とは?-
おはようございます。
今日7月3日はその語呂から涙の日と制定されていてドライアイケアの必要性などが呼びかけられます。
ここ数年、私も歳のせいか目に疲れを感じるようになりました。
紙媒体で行なっていた伝票処理など仕事の殆どがデジタル化になり、一日中パソコンを見ながら仕事をすることも増えました。
加えて、スマートフォンを持つようになり、休み時間にネットニュースやユーチューブなどを見ることも多くなり、目の負担は昔に比べて相当なものとなっていると思います。
今は会社員の9割が仕事上パソコンを使用すると言われており、パソコンの使用を辞めるわけにはいきませんが
ちょっとした工夫や心がけで、疲れ目を軽減させることは可能です。
今日は何個か疲れ目の対策を紹介します。
●適度に休憩をはさむ
仕事の生産性の高い人は、必ず1時間に一度は休憩を取っているという調査結果が出ているそうです。休憩は一気にとるのではなく、こまめに取ることで目の疲れはもちろん、脳のリフレッシュにもなります。
●ストレッチをする
目の筋肉のストレッチをすることで眼精疲労が取れます。1時間に1分程度行うと効果的で目を閉じて眼球を左右や上下に動かしたり、ぐるぐる回したりするだけでも効果があるそうです。
●パソコンを調整する
そもそもの原因としてパソコンを使用する環境が悪い場合があります。
・画面を目の高さと同じか少し低めにする
・ディスプレイの明るさは、室内の明るさと同じくらいにする
・椅子の背もたれにお尻が付く
・足裏全体が床につくように椅子の高さを調節する
など目が疲れにくい環境を作ることができます。また最近ではブルーライトをカットするメガネや寝る時に目を温めるような商品も出ています。
目は人間の五感の中で一番重要な部位だとも言われています。
仕事で疲れたなと感じたときには、しっかりと休むことも大切です。
カレンダーでみる7月の朝礼ネタ・スピーチ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2023年7月 最新のニュース・時事ネタの朝礼・スピーチ
行事や生活でみる7月の朝礼ネタ・スピーチ

7月の旧暦は「文月(ふみづき)」。語源には色々な説がありますがその中の一つに、稲の穂が実る頃という意味の「穂含月(ほふみづき)」が転じて「文月」になったという説があります。

全国安全週間は、例年7月1日から7月7日の1週間、災害や事故防止活動の推進と安全に対する意識のより一層の向上に取り組む週間で全国的に行われます。

2023年は7月13日~7月22日が夏の交通安全運動とされており、警備の強化や交通事故防止の徹底が謳われます。

7月7日といえば七夕祭りです。七夕とはお盆行事の一環でもあり、精霊棚とその幡を安置するのが7日の夕方であることから7日の夕で「七夕」と書いて「たなばた」と発音するようになったという説もあります。

海の日は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」という国民の祝日です。 1996年から国民の祝日「海の日」となり、2003年には7月の第3月曜日に変更されました。

7月第4日曜日は「親子の日」と制定されています。写真家ブルース・オズボーン氏の呼びかけによって2003年から始まった社会的な活動です。 年に一度、親と子が共に向かい合い、語らいながら、親子の絆を深める日として、あらゆる地域、世代の方から共感を集めています。2023年は7月23日(日)が親子の日です。

土用干しというのは、夏の土用の時期に行われる行事の一つで、衣類とか、書物といったものを文字通り「干す」日です。

土用とは、「季節の変わり目の約18日間」のことをいいます。身体を壊しやすい季節の変わり目にウナギを食べてエネルギーを蓄えましょう。2023年は7月30日です。

7月は太陽の光をたくさん浴びて、栄養がギュッと詰まっている夏野菜や果物が多い時期です。

7月から本格的な夏が到来し、各地で熱中症警報が出されます。水分補給や体温調節など注意する点は多いです。

地球温暖化対策活動の一環として、冷房時の室温28℃を目安に夏を快適に過ごすライフスタイル。過度な冷房に頼ることなく、様々な工夫をして夏を快適に過ごす取り組みです。地域にもよりますが5月1日~9月30日の期間に推奨されています。

道教の年中行事である「中元」が起源といわれています。首都圏では7月上旬から15日ごろまでに贈るのが本来の習慣。首都圏以外は7月上旬から8月15日ごろが中元の期間です。

小暑(しょうしょ)は、二十四節気の一つで、夏の始まりを告げる節気です。毎年7月7日前後に訪れます。






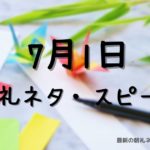
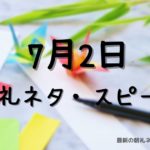
コメント