
七五三の日

徳川将軍家の「袴着の儀」がおこなわれた日が踏襲されて11月15日が子供の成長を祝い、氏神様・産土神様に報告をおこなう日として七五三の日と制定されています。
朝礼ネタ:11月15日 七五三の日-七五三のそれぞれの意味-
(例文)11月15日 七五三の日-七五三のそれぞれの意味-
本日11月15日は七五三の日です。
10月から11月に行われることが多い七五三ですが、七五三の由来である江戸幕府第5代将軍の徳川綱吉の長男の健康を祈ったのが1681年のこの日ということから、11月15日が七五三の日といわれているそうです。
私は七五三の歳に写真を撮る行事という認識しかなかったのですが
七五三という歳にも意味があるそうで
3歳は髪を伸ばす「髪直」
(昔は3歳までは髪を剃っていたそう)
5歳は初めて袴をつける「袴着」
(男の子が袴をつける儀式)
7歳は本仕立ての着物と丸帯という大人の装いをする「帯解」
(女の子が大人と同じ幅の広い帯を締める儀式)
をそれぞれ祝う意味があります。
また七五三といえばなんといっても千歳飴ですが
この千歳飴も祈りがこめられていて
千歳という名の通り、「千年生きて欲しい」という長寿の願いがこめられています。
日本独自の文化には一つ一つに必ず意味があり、そして必ず由来があります。
その日本文化の奥深さが近年では外国人に興味を持たれ、日本の良さがクローズアップされることで日本人が再確認することも増えてきています。
私も日本人として、日本の古き良き伝統を守り、そして日本の良さを伝えていかなければならないと思います。
昆布の日

11月15日の「七五三」の日に、育ち盛りのお子さんが栄養豊富な昆布を食べて、元気に育ってほしいという願いから昆布の日と制定されています。
朝礼ネタ:11月15日 昆布の日-昆布が海の中で出汁が出ないのなんでだろう-
(例文)11月15日 昆布の日-昆布が海の中で出汁が出ないのなんでだろう-
今日11月15日は「七五三」ですね。この日に、育ち盛りのお子さんが栄養豊富な昆布を食べて、元気に育ってほしいという願いから昆布の日とも制定されています。
テツandトモさんのネタで、昆布が海の中で出汁が出ないのはなんでだろう?というのがありますが、理由をご存じですか?
昆布は生きているときは出汁が出ないんだそうです。
海中で生きている時はグルタミン酸などのうまみ成分が細胞膜に覆われて守られているので出てこないのです。
しかし昆布は海から引き上げられると死んでしまい、太陽に当てて乾燥することによりこの細胞膜が壊れて、さらにこれを水につけることによってうまみ成分が出てくるというしくみになっています。
ちなみに、煮干しや豚骨も死んでいるものを加工して初めて出汁が出ます。
昆布も生きているときは栄養が出てしまわないように必死に自分の体を守っているということです。
ということで今日は少し雑学を披露してみました、
カレンダーでみる11月の朝礼ネタ・スピーチ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
日付をクリックで朝礼ネタにとびます
2023年11月 最新のニュース・時事ネタの朝礼・スピーチ
行事や生活でみる11月の朝礼ネタ・スピーチ

2005年に環境省が提唱して始まりました。暖房に必要なエネルギー使用量を削減することにより、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。

乳幼児の死亡率が高かった時代、七歳までの子供は神の子とされ、七歳になって初めて社会の一員として認められました。その儀式が、明治時代になって現代の七五三として定着したと言われています。

勤労感謝の日は戦後国民の祝日が定められた際に「勤労をたっとび、 生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」という趣旨で定められました。

ボジェレー・ヌーヴォーは、その年に収穫されたブドウで造られた新酒であり、ブドウが良質であるかを確認するためのものでもあります。毎年11月の第3木曜日午前0時に販売が解禁されます。

米国の感謝祭(11月第4木曜日)の翌日の金曜日のことをブラックフライデーと指します。感謝祭の売れ残り需要から買い物客による混雑、または黒字を連想させることから「ブラックフライデー」と名付けられました。

毎年11月に消防庁が秋から冬にかけての火災が発生しやすい季節を迎えるに当り、広く防災意識を高めることを目的として制定しています。

「11」という数字は1と1が対等であることから、男性と女性が性別を越えて一緒に取り組む参画週間と制定されています。











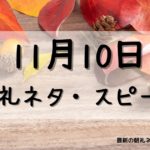
コメント