最新のニュース

9月1日、関東大震災から100年の「防災の日」 を迎え、各地で防災訓練が行われました。
朝礼ネタ:関東大震災から100年-意外と知られていない2つの行動-
(例文)関東大震災から100年-意外と知られていない2つの行動-
おはようございます。
先日9月1日は「防災の日」でした。1923年に発生した関東大震災からちょうど100年が経ったということで各地で防災訓練が行われたようです。
震災は、いつどこで起こるか分からないからこそ、日ごろの備えが非常に重要です。
では実際に巨大地震が起きたときにするべき行動はなにか?
今日は意外と知られていない行動2つを紹介します。
ではまず、停電が起きて避難所に避難を余儀なくされた時。あなたは何をしますか?
災害グッズの確保や貴重品などの携帯、色々とやるべきことはあるかと思いますが意外と知られていないのが
「ブレーカーを切る」ということです。
避難中に電気が復旧したとき、起こりうるのが通電火災。その通電火災を防ぐためブレーカーを切るのです。実は地震による火災でこの原因の火災が多いのです。
ではもう一つ。
あなたがエレベーターに乗っていたとします。揺れを感じた時あなたはどうしますか?
この場合「全ての階のボタンを押す」ことが最善策です。
地震によるエレベーター内の閉じ込めも意外と多く、巨大地震の場合、救助や復旧にも時間がかかり結果的に避難することすら出来ずその場で待機なんてこともあり得ます。
地震を察知したときには全ての階のボタンを押し、最寄り階で降りること。そして階段を使い避難をする。これがベストな行動です。
まだまだありますが、知っておくのと知らないのとでは実際に地震が起きたときにする行動が変わってきて、結果的に命に関わります。
日頃からいろんな想定をして、訓練しておきましょう!
カレンダーでみる9月の朝礼ネタ・スピーチ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
日付をクリックで朝礼ネタにとびます
2023年9月 最新のニュース・時事ネタの朝礼・スピーチ
行事や生活でみる9月の朝礼ネタ・スピーチ

がん・心臓病・脳卒中・糖尿病などの「生活習慣病」や、運動・食生活などの「個人の生活習慣の改善の重要性」についての国民一人ひとりの理解を深め、健康づくりの実践を促進するために制定されています。

地球温暖化対策活動の一環として、冷房時の室温28℃を目安に夏を快適に過ごすライフスタイル。過度な冷房に頼ることなく、様々な工夫をして夏を快適に過ごす取り組みです。地域にもよりますが5月1日~9月30日の期間に推奨されています。

9月1日の「防災の日」を含む一週間を防災週間と定められています。

2002年まで9月15日は「敬老の日」という国民の祝日だったが、2003年から「祝日法」の改正によって「敬老の日」が9月の第3月曜日に変更されたのに伴って、この日が「老人の日」と制定されました。
この日から一週間の9月15日~21日は「老人週間」となっている。

十五夜のお月見が広まったのは「平安時代」。月を眺めながらお酒を飲んだり、船の上で詩歌や管弦を楽しんでいたのが始まりです。

9月24日の清掃の日から10月1日の浄化槽の日までの1週間は環境衛生週間
とされており、廃棄物を極力減らす、資源の再利用、適正なゴミ処理量を念頭に様々な提唱や認知活動が行われております。

9月21日から9月30日は秋の全国交通安全運動とされており、国民一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践することが呼びかけられております。

白露(はくろ)は、二十四節気の一つで、夜中に大気が冷え、草花や木に朝露が宿りはじめる頃をいいます。毎年9月9日前後に訪れます。

秋分は、1年の中で昼と夜の長さがほぼ等しい日、太陽が天球上で天赤道を南から北へ横断する時点を指します。秋分は通常、9月22日または23日頃に起こり、この日を境に日が短く、夜が長くなり始めることが特徴的です。








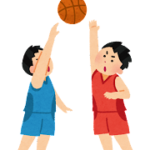

コメント